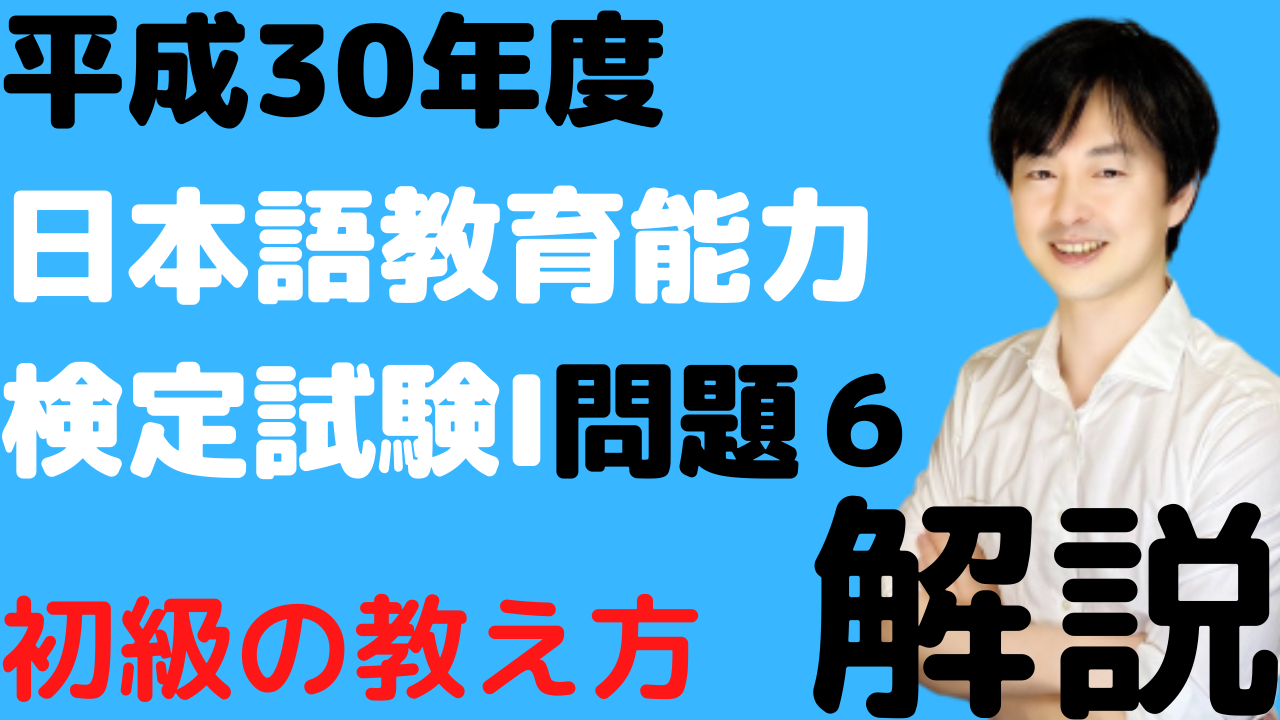平成30年度(2018)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ問題6は【初級と日本語指導】です。
問1【帰納的アプローチとは】
解き方
帰納的アプローチ(帰納法)とは、具体的なことから一般的なルールを見つけるアプローチ
- 「効率的に文法規則が指導できる」のは、演繹的アプローチ(演繹法)です。
- 「初級の日本語指導」で「無作為に収集した例文」を使用しても学生は理解できないと思います。
- 学習者が自らルールを発見することで深い理解につながるのが帰納的アプローチのメリットです。
- 「原理的な文法説明」といえば演繹的アプローチです。
よって、答えは3です。
帰納的アプローチと演繹的アプローチの違い
帰納的アプローチでは、具体例をいくつか提示して、そこから一般的に言えることを探します。学生にルールを見つけてもらうので、教師がルールを提示するのに比べると非効率です。
演繹的アプローチでは、まず文法などのルールを教えて、次にそのルールの具体例を提示して、最後に練習をします。
演繹的アプローチでは、まずルールの説明から入るので、原理的な文法説明を好むタイプの学習者はこちらが好きですね。ドイツ系の学生に多い気がします。
| 帰納的アプローチ | 具体→一般 |
| 演繹的アプローチ | 一般→具体 |
帰納的アプローチを使った動詞の活用形の導入
私は新しい動詞の活用(フォーム)のルールを扱う時、帰納的アプローチを使います。
T「グループ1の動詞は何がありますか?」
S「書く、読む、話す」
T「(板書しながら)可能形は、書ける、読める、話せる、です。グループ1の可能形のルールがわかりましたか?」
S「u→eる」
というような流れでやります。帰納的アプローチでは、自分でルールを発見した喜びが得られるので、私が学習者なら帰納的アプローチの方が好きですね。
問2【初級における媒介語の使用】
解き方
媒介語とは、媒介する語。媒介とは間に入って仲立ちすること。例えば日本語を教える時に英語を使う場合、英語が媒介語です。媒介語と言えば直接法と間接法ですね。
直接法とは、媒介語を使わずに日本語で日本語を教える方法
間接法とは、媒介語を使って教える方法。日本語の文法や言葉の説明を英語でしたり学習者の母国語でしたり。
では選択肢を見ていきましょう。
- 時間の経済性とは効率のことですね。初級の学習者は理解できる言葉が少ないので媒介語を使った方が効率がいいです。マル。
- 私の働いている日本語学校は直接法で教えていて英語禁止なのに、中級になっても英語で質問してくる学習者がいます。初級の頃から媒介語に依存しすぎないよう気を付けた方がいいです。マル。
- 「教室でよく使用する表現」であれば、簡単に覚えらえるので媒介語を使う必要はありません。例えば、「聴いてください」とか簡単な指示語は初日に教えます。バツ。
- 「社会的・文化的背景についての説明」は、日常的な話に比べて難しいので、媒介語の使用が有効ですね。マル
よって、答えは3です。
問3【オーディオ・リンガル・メソッドの文型練習のやり方】
解き方
オーディオ・リンガル・メソッドとは、アーミー・メソッドを一般化したもの。つまり、鬼教官「オーディオ」大佐による厳しい反復練習をイメージしてください。それです。そのイメージで各選択肢を見ていきましょう。
- 鬼教官「オーディオ」大佐はまずお手本を見せた後、まず全体で練習させます。そのあと個別練習に入ります。マル
- 鬼教官は細かい誤りを許しません。バツ
- 鬼教官「オーディオ」大佐は名前の通り「音」を重視します。つまり口頭練習です。書くドリルのことではありません。バツ
- 鬼教官「オーディオ」大佐は全体練習の後は、学習者同士での訓練もさせます。バツ
よって、答えは1です。
教授法の覚え方
メソッド(教授法)は似ている言葉が多いので言葉をそのまま暗記しようとするのではなく、イメージと結び付けてください。これは精緻化リハーサルといって長期記憶に残りやすくなります。オーディオ・リンガル・メソッドは、竹刀を持った鬼教官「オーディオ」の命令で、腕立て100回、腹筋100回、スクワット100回を繰り返しやらされている(「私はオーディオ先生が好きです」と叫びながら)絵をイメージしてください。
問4【パターン・プラクティスの応答練習の例】
応答練習とは、問いに応じて答える練習。つまりQA
- 「毎日、テレビを見ますか」「はい、見ます」QAですね。これが応答練習
- 「テレビを見ますか」の「テレビ」のところに「映画」に代入しているので代入練習
- 同じ言葉を繰り返しているので模倣練習。リピート
- 「見ます」「見ません」教師の言葉を否定形に変形しているので変形練習
よって、答えは1です。
問5【コミュニケーション能力の養成に効果的な練習方法】
解き方
試験Ⅰ問題3A(2)の解説で「不適当なものを選ぶ問題で、答えがわからない場合、知らない言葉を選ぼう」と話したかと思いますが、逆も言えます。
「適当なものを選ぶ問題で、答えが分からない場合、知っている言葉を選ぼう」
このスキルはいつも成功するわけではありませんが、何も考えずにやるよりは確率が上がります。この選択肢を見て、イメージしやすいのは2と4ですよね。4のディクテーションは英語学習でも聞いたことがあるかと。ディクテーションとは、聞いた音を書きとること。話さないのでコミュニケーション能力はちょっと…。2のシナリオ・プレイはなんか劇とかやりそうなイメージの言葉ですよね。劇はコミュニケーションだからコミュニケーション能力の養成に効果的! よって、答えは2です。
言葉の意味
ラポート・トークとは、感情に働きかける話し方。自分の気持ちを述べたり共感を示したり。ラポールのトークですね。ラポールは結構、日本語教育能力検定試験に出てきます。ラポートトークは女性が好む話し方といわれています。
リポート・トークとは、情報を淡々と伝える話し方。リポーターの話し方ですね。リポートトークは男性が好む話し方といわれています。
シナリオプレイとは、シナリオ(脚本)をプレイする(演じる)こと。まずはモデル会話のシナリオを覚えてペア練習。そこから発展させていくという練習方法を私はよくやります。役を演じるので会話しやすくて、コミュニケーション能力の養成に効果的です。
フォローアップ・インタビューとは、何かの後のフォローアップ(追いかける・追跡調査)のためにインタビューすること。会話の練習方法ではないですね。例えば、人を集めた実験の後日、被験者に改めてインタビューすること。
関連する過去問
・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5【パターン・プラクティスの1つである拡張練習の例を選ぶ問題】
・平成26年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6【演繹的指導と帰納的指導】