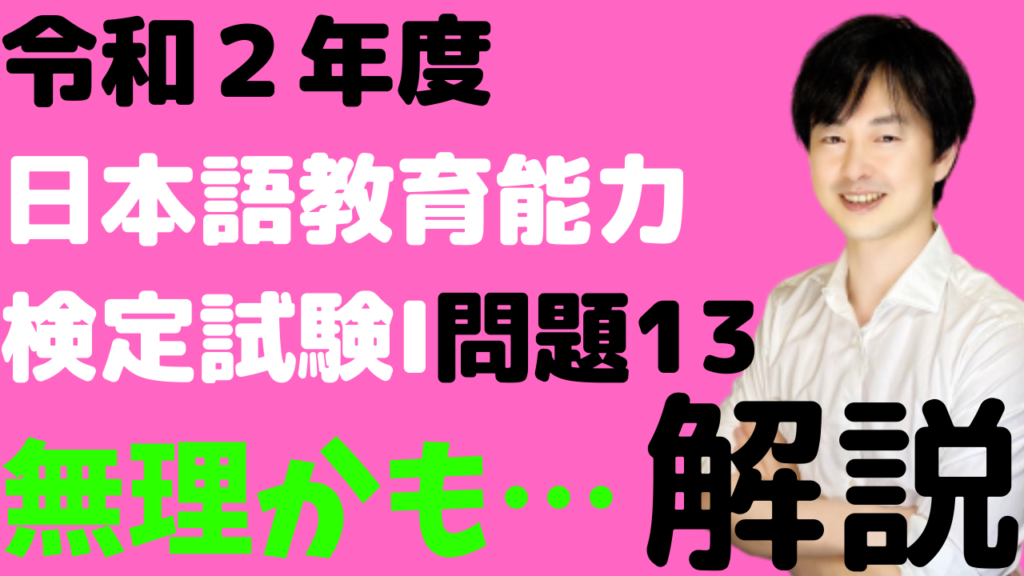令和2年度(2020年)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ問題13【コミュニケーション上の行き違いが生じる理由とは】の解説です。
問1 会話で統語レベルの誤解が起こっている例
コミュニケーションで行き違いが生じる時、音韻レベル、統語レベル、意味レベルの誤解が考えられます。
音韻レベルの誤解とは、聞き誤りです。
統語レベルの誤解とは、文の構成の誤りです。
意味レベルの誤解とは、言葉の意味を勘違いした誤りです。
それぞれの選択肢を見ていきます。
選択肢1 「あれを取って」の「あれ」の指示対象を誤って解釈
「あれ」の意味を勘違いしているので、意味レベルの誤解です。
選択肢2 「小さな猫の声」の修飾関係を誤って解釈
猫が小さいのか(小さいが猫を修飾)
声が小さいのか(小さなが声を修飾)
何を修飾しているのかは文の構成に関わりますので、統語レベルの誤解です。
選択肢3 「沢田さん」を「真田さん」に聞き誤って解釈
聞き誤っているので、音韻レベルの誤解です。
選択肢4 断り表現の「結構です」を承諾と誤って解釈
「結構です」の意味を勘違いしているので、意味レベルのごかいです。
よって、答えは2
問2 高コンテクスト文化とは?
覚えていますでしょうか?
高コンテクスト文化と低コンテクスト文化といえば、令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8の問1でも聞かれました(高コンテクスト文化という言葉はでてきていませんが)。
え? そうだったけ?
という方は下の動画をどうぞ。
高コンテクスト文化とは?
高コンテクスト文化とは、空気を読む文化
発せられた言葉の意味がその状況、文脈(コンテクスト)に依存する。言葉の表面的な意味でなく、相手の感情を察することを要する。
例えば、デートの約束をしている女性から「ごめん、今日の約束ちょっと厳しいかも」と言われたとき、「ちょっと」だし「かも」だから、まだまだいける可能性が高いな! と判断してはいけない。Noとはっきり言いづらいので表現を和らげているに過ぎず、実際にデートが実現される可能性は限りなく0に近い。これが高コンテクスト文化である。
選択肢1のように「個人間で共有された情報・経験を前提に伝達が行われる」
低コンテクスト文化とは?
低コンテクスト文化とは、「言わなきゃわからないよ」の文化
イエスならイエス、ノーならノートはっきり言う。相手が察してくれることは期待しない。大切なことは全て言葉にする。例えば、ドイツ人といえばルールに従うことで有名ですが、ドイツ系は低コンテクスト文化の傾向が強いです。言葉にされたことは理解するし、言葉にされていないことは知らないということ。
選択肢2から4のように「個人主義的で、互いに意見がはっきりと述べられる」「問題解決の際、回避せず直接的な話し合いが好まれる」「相手の発話がそのまま文字どおりの意味で解釈される」
よって、答えは1
問3 否定応答の例
またきたか。
日本語教育能力検定試験の過去問をたくさん解いている皆さんはこう思ったことでしょう。
そうです。
応答の種類は日本語教育能力検定試験の大好物で、過去に何度も出題されています。
え? そうだっけ? という方は、平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題12を要チェック
今までは、優先応答、非優先応答という分け方が多かったですが、今回は、肯定応答、否定応答、回避等にわけられています。
わかりやすくなっていますね。
肯定応答とは、相手の発話に対して肯定的な応答
否定応答とは、相手に発話に対して否定的な応答
選択肢を見ていくと、1から3はポジティブな対応。4はネガティブな対応
よって、答えは4
問4 逸脱に対する評価や調整
「逸脱に対する評価や調整」とあえて難しい言葉を使っていますが、下線部の前を見れば簡単ですね。
「円滑なコミュニケーションを目指して」
これです。
母語話者は非母語話者と話すときに、円滑なコミュニケーションを目指してどんな工夫をするか、
考えながら選択肢を見ます。
選択肢1
非母語話者が言葉を理解できなかったときは、簡単な言葉で言い換えたり、もう一度いったりします。
マル
選択肢2
「言語的な逸脱」と難しい言葉を使っていますが、要は、言語に関する間違い、音声が違っていたり、語彙が違っていたり、文法が違っていたり。
A:(苦痛の表情でお腹をさすりながら)ここ、ここ…
B:お腹痛いの? 薬いる?
このように、Aは「お腹が痛いんですけど、薬をくれませんか」という言葉が言えなくても、Bが先取り発話をすることで、会話を支援します。
マル
選択肢3
社会言語的な逸脱とは、文法に誤りはないけど、社会的に不適切な言葉に使用。先生にタメ語で話したり。
これは実際によくあります。日本人の友達が多くて、普段からタメ語(友だち言葉)を使っている学生は、先生にもタメ語で話してきますが、その場合、私はイラっとして、否定的な評価をしてしまいます。
バツ
選択肢4
談話生成上の逸脱とは、会話の組み立ての誤り。
A:今日は、とても寒いですねー。
B:うん。
A:1万円、貸してくれない?
B:え、どうしたん? 急に?
もし、Aが談話生成を適切に行うとすれば、「1万円、貸してくれない」と言う前に「ところで」を使って話題を変えたり、最近、お金に困っている事情を話したりして段階を踏んでお金が貸してほしい、という気持ちを伝えます。なので、Aは談話生成上の逸脱を犯したと言えますが、Aが非母語話者であることを考えれば、Bも深刻な誤りだとは捉えないでしょう。貸すかどうかは別問題ですが。
よって、答えは3
問5 意味交渉の例
意味交渉とは?
意味交渉とは、発話で誤解が生じないよう工夫すること。明確化要求、確認チェック、理解チェックがあります。
意味交渉の仕方の例については、平成28年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題13に出てきますので要チェック
明確化要求とは?
明確化要求とは、相手の言っていることが不確かなときに、明確にするよう要求
例)
A:今日の約束、やっぱり無理かも…。
B:え、「無理かも」ってどういうことですか? 何%ぐらいの確率で無理なんですか?【明確化要求】
A:…
確認チェックとは?
確認チェックとは、相手の言ったことを自分が正しく理解しているか確認
A:今日の約束、やっぱり無理かも…。
B:「かも」ということは、まだまだ期待していいんですよね?【確認チェック】 3時に渋谷駅ハチ公前にいますね。
A:え…
理解チェックとは?
理解チェックとは、自分の言ったことを相手が正しく理解しているか確認
A:今日の約束、やっぱり無理かも…。
B:「かも」ということは、まだまだ期待していいんですよね?【確認チェック】 3時に渋谷駅ハチ公前にいますね。
A:え…
B:渋谷駅ハチ公前であなたを待っていると言うことですよ。私の話、わかりましたか?【理解チェック】
各選択肢を見てみると、2は自分の理解を確認しているので意味交渉の確認チェックです。
よって、答えは2